遠藤周作という人の存在はこれまでも知っていたけれど、その本を手にする機会がこれまでありませんでした。
本書は月刊ペントハウスの1984年から1987年まで同タイトルで連載されていた合計44回のうち39回分を収録したもの。(5回分はどこに行ったのだろう?)
それにしても「読んでもタメにならない」とは、なかなか天邪鬼な副題です。
雑誌のカラーや想定される読者層を考慮してか、俗物的とも思える内容が散見されていましたが、著者一流のユーモアを織り交ぜて語られる処世術(?)の内容は示唆に富んでいるものも多分にあり、視点のユニークさや豊かな知見にあふれています。(21世紀の現代から見ると、少々時代を感じるところもあります)
けれど、最も感銘を受けたのは最終章「私の言いたかったことを要約しよう」のところです。
教育の過程において「合理的に物事を考える」「科学的に物事を見定める」ということを身につけ、それが正しいと考えるのが良識のある人たち。
けれど、遠藤周作さんはこんなことを言っています。
この世には合理的な考え方が当てはまることも多いが、これに当てはまらぬものもある。当てはまらぬものをハナから馬鹿にするな、と私は言いたいのだ。
本文より抜粋
一見すると時代にそぐわないようなこと、そんなことをエッセイで荒唐無稽に話したのなら、良識のある人たちにとってはきっと「タメにならない」と思うでしょう。けれど、それは本当に「タメにならない」のかな?
天邪鬼のような副題には、著者のそんな気持ちが反映されていたのでした。
このエッセイが書かれたのは1980年代ですから、もうかれこれ35年も前のこと。その当時、すでに遠藤周作さんには新しい時代の足音が聞こえていました。
新しい時代、これからの時代にはどんな考え方が求められるだろうか、合理的、科学的でないものをナンセンスと切り捨てず、ちょっと眺めてみてはどうだろうか、もしかしたら面白いものが見つかるのではないか?
そういったことを、大上段に構えて講釈を述べるのではなく、茶の間でお酒でも飲みながら冗談を言いながら雑談するように話し、そんな中から何か新しい息吹を感じてもらえないだろうか、そんなことを遠藤周作さんは考えていました。
一見すると俗物的なエッセイのようで、その根底にはそんな強い著者の想いが強く流れています。そう思って改めて本書を眺めた時、これは単なるエッセイ集ではない、確かにこれは「塾」でした。
本書を読んで、遠藤周作という人の知性の片鱗に触れたような気がしました。
これから、他の作品も順番に読んでみたいと思っています。どんな遠藤周作ワールドが待っているのか、楽しみです。
以上です。
最後まで読んでいただいて、ありがとうございます。
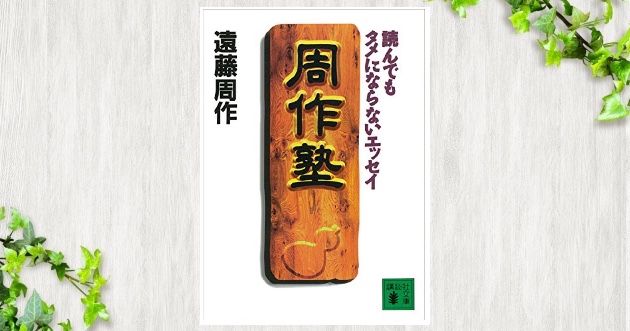

最近のコメント